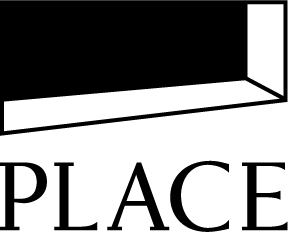10分くらいだろうか。
ガタンガタンとリズムを刻む列車の小気味いい振動とうららかな陽射しに誘われてつい微睡んでいた。
起きぬけのジーンとする頭をもてあましながら車窓越しの景色に目をやる。
視界いっぱいに広がる田園風景、ひとりトラクターに乗り作業をするお爺さん、ぽつぽつと建つ民家、そのさらにずっと奥には春の彩りをまぶした山々が午前の陽を浴びて白い光をまとっている。
あれ。今はどの辺を通過しているんだっけ?ふと浮かんだ疑問をかき消すように列車は真っ暗なトンネルに入り、今見た景色は一瞬で過去のものになる。
・・・・・
3月末から1週間ほど「青春18きっぷ」をおともにして一人旅をしていた。僕の住む東京から山口県の下関まで6日間かけてめぐる列車旅だ。
(知らない方もいるかもしれないので説明すると、「青春18きっぷ」とはJRが発行している春と夏の一定期間使える切符のことで、この切符一枚(12,000円弱※2018年現在)で日本中のJRの「鈍行」だけを5日間利用することができる。18歳限定で利用できるというわけではない。おそらく“18歳的な旅”ということなのだろう。だから青春というわけだ。たぶん)
飛行機や新幹線を利用できないから移動時間がとにかく長い。1日の大半は移動時間で費やしてしまう。
列車に乗り(どうして旅の話になると「電車」ではなく「列車」と言いたくなるのだろう)、移りゆく景色をぼんやり眺める。眺めることに飽きれば西尾勝彦さんの詩集『歩きながらはじまること』を開き言葉を追いかける。窓から射し込む陽の光と影が紙の上に落ちては消え言葉に濃淡を作る。
詩のもつリズムと列車の車輪が刻むリズムは相性が良い。そのリズムがまた眠気を誘いしばし微睡ませる。目を覚ませばまた過ぎ去る景色を眺める。基本的にはその繰り返しだ。
目を覚ます度に景色は変わる。
街から山へ。山から海へ。海から街へと。
窓から望む田園風景の中にぽつぽつと数えられるだけの人の姿を見つける度に、矛盾するようだけれど「人ってたくさんいるんだな」と思う。毎日東京で人混みに埋もれ、何千何万という人の顔を見ているのにも関わらず。
「身の丈を知れ」という言葉が眼前に浮かぶ。
東京は「もしかしたら」の街だ。望むと望まざるに関わらず、もっと高く、もっと遠くに理想があると、誰かを、何かを引き合いに出して際限もなく投げかけてくる。可能性と呼ぶにはあまりに頼りない「もしかしたら」を腕いっぱいに抱えた僕らは、時に高を括り、時に嘆いたりして今日もまたひとつの「もしかしたら」を探す。もっとないのか?と誰に向けるでもなくせがむように。
目の前の景色は「あなたは、ただ人ひとり」だと語りかける。何者でもないただひとりであることを自覚せよと諭してくる。東京で聞けばネガティブに響くようなこんなフレーズも、この景色の中では不思議と励まされる言葉として響く。なんなら高揚さえした。
何者でもないということは少なくとも“他の誰か”ではないということ。「身の丈を知る」とはつまり、他の誰かではない自分を自覚し役割を探し始めるスタートのことであり、それは「もしかして」を外ではなく自身の中から芽生えさせる決意のようなものではないだろうか。
そのことに気付き少し安心して僕はまた微睡みかける。
「特急列車を見送るため10分ほど停車します」
何度目かの微睡みをアナウンスの声が断ち切る。
乗客がまばらな中でシンと静まる車内。
束の間の静寂の中でふと「文通したいな」と思う。
直筆の手紙のやりとりにこだわるわけではなく(それはそれでしてみたいけれど)、じっくりと相手と自分の気持ちと向き合い、何度も書き直しながら文章にしたためて送り、数日後か数週間後に返信が来る「文通」のような“遅い会話”がしたい。
“遅い会話”には相手のことを考え言葉を紡ぐために、ある一定以上の時間が必要になる。相手も自分のためにその時間を持ってくれているはずだという“認識の交換”が、普段の暮らしのひとつの拠り所(拠り所という言葉が大袈裟なら安心と言い換えてもいい)になる、そんな気がしたのだ。
早く多くの人とつながれる普段のオンライン上の言葉のやりとりに手応えがないわけではないし、今さらその利便性を手放したいとはさらさら思わないけれど。
時間が許す限り列車を降りては街を歩いた。
一人で旅をしていると色んな人の声が耳に入りやすくなる。
これといった理由などない。ただ単に暇だからだ。
京都の喫茶店でモーニングをとっているときのことだ。
僕の隣には長年連れ添ってきたであろう老夫婦が座っていた。奥のソファ席に奥さんが座り、手前のテーブル席にご主人が座っていた。
ご主人が朗らかに話しかけても奥さんの方は「あぁ」「そうね」と返すだけ。
「つれないな」と僕は思う。それでも殺伐とした雰囲気はなく、どことなく牧歌的な光景に映る。
朝食を食べ終えた奥さんが「ちょっとお手洗いに」と席を立つ。
奥さんは脚が悪いようだ。少し足を引きずりながらトイレに向かう。奥さんの姿が見えなくなると、ご主人はいつも決められた作業のように自然に立ち上がり、奥さんの座っていたソファ席に移る。
数分後、お手洗いから戻った奥さんは旦那さんが座ってた手前の席に、つまりはお手洗いからより近い席の方に当たり前のように座った。
数分の静かな時間が流れる。
「じゃ。そろそろ会計しようか」と旦那さんが促せば「そうね」と立ち上がる奥さん。
何気ない風景、何気ない会話、何気ない日常だ。
それでもそこには控え目であたたかい気持ちの交換があった。
「旅は非日常だ」と言う。
たしかにそれはそうなのだけれど、僕が旅先で感じたのはどうしようもないくらいの「日常」だった。
感じるというより「思い出す」のだ、みずみずしい会話を、ひとり思い耽る時間を、そんな代わり映えがなくてとりとめもない、ただただ愛おしい日常を思い出すのだ。
だから、旅をしよう。
僕らにはもっと「日常」が必要だ。
文・写真:Takapi