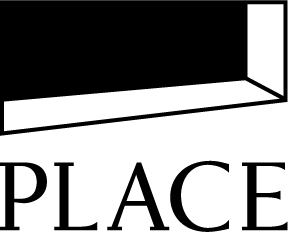9月の最終週に、遅い夏休みをもらってラオスのルアンパバーンを旅行していた。
なぜ数ある国の中から旅先としてラオスを選んだのか。その答えは村上春樹の『ラオスにいったい何があるというんですか?』にある。読んでもらえればきっと「あぁ。あれを読んだなら仕方ないね」となってくれると思う。
結論から言ってしまえば、ラオスの旅はとてもいいものだった。本当はここで旅の詳細を語りたいのだけれど、行程を追いかけはじめるとこのコラムの標準的な文字量(もしそういうのがあるなら)を超えてしまうので、印象に残った一部のシーンだけをつらつらを書き連ねることにする。
ラオスという国について、旅先としてどんな楽しみがあるかを知りたい方は、先ほど紹介した村上春樹の本を読んでみてください。
さて、ラオスに来て一番はじめに驚いたのは、通りを行き交うバイクの量だった。主な交通手段がバイクであることにも少し驚いたが、どう見ても中学生くらいにしか見えない子が自転車のように乗り回していること、そしてそのほとんどが日傘を差していることに、思わず「違反切符!」と叫びそうになった。
ただ、しばらく通りを眺めているとそんな光景も慣れてくるようで、日傘がひとつのファッションアイテムとして機能していることに気付く。フリルのついた紫の傘、顔のモチーフがついた黄色の傘(ポケモンかな)などが、時には主張し、時には差し色のように全体のコーディネートの一端を担っていた(見当違いかもしれないけれど)。
人間と自然の距離が近いこともラオスに来て感じたことだ。
露店の脇や家の前には犬が寝そべり(そのほとんどが平和な顔をしている)、建物の至るところにヤモリが張り付き(僕らが泊まったホテルの部屋にも3匹ほどが“見張って”くれていた)、ニワトリはいつもせわしなく駆け回り、けたたましい鳴き声でモーニングコールを鳴らす。おかげで毎朝5時過ぎに起きることになった。
毎朝通りで行われる朝市では、カエルの丸焼きや、しめたばかりのニワトリ、ハエのたかった肉のかたまり、メコン川で採れたであろうぞっとするような形の魚など、おもわず足がすくんでしまう光景が目の前に拡がる。
その通りを抜けるとカフェオレ色のメコン川(つまり泥水だ)が静かに、それでいて圧倒的な大きさで街を取り囲むように流れている。どのくらい大きいかと言えば、大雨が降り洪水が起きたら、一瞬でこの街を沈めることができるとわかるくらいには、大きい。
泥水が静かに流れているというのは、日本人からしたらなんとも不思議な光景に映るのではないだろうか。日本において川が泥水になるのは、ほとんどの場合大雨が降ったあとの濁流のときくらいで、それは轟音を響かせながらものすごいスピードで目の前を駆け抜けてゆく。
静かに泥水が流れているというのは(しかも圧倒的な量で)、はじめのうちは不気味に映る。その水がどの程度の深さなのか、その中に何が生きているのか、まったく(本当にまったく)わからないのだ。ただ、それも1日経てば慣れてくる。その雄大さに畏敬の念さえ浮かんでくるのだ。不思議なものだ。
ルアンパバーンのメインの通りでは、毎日ナイトマーケットが開かれている。日が暮れ始めると徐々に人が集まり、テントの設置を始め、通りに敷いたござの上に刺繍の入った布物やお皿や絵などが並べられる。
そんな風にして、誰が号令をかけることもなく静かにナイトマーケットは始まる。それは日暮れとともに始まり夜10時まで続く。
ここでは、昼間は小学校や中学校に通っていたであろう女の子もお母さんと一緒に店番をしている。店の前を通ると、声をかけるではなく、控え目な笑顔で「どうぞ」と無言で接客をしてくれる。
僕が刺繍の入った小物入れを買ったときに相手をしてくれたのは、15歳くらいの女の子だった。
僕が値段を聞くと、電卓を叩き僕に見せてくれた。並ぶ数字は現地のお金なので、それが高いのか安いのかすぐには判断できず、頭の中で円換算をしていた。
少しの間。その間を彼女は「渋っている」と感じたのか、すぐに電卓を引っ込め、隣にいるお母さんと2、3言葉を交わしてから、先ほど提示した数字の2/3の数字を電卓に打ち込んで僕に見せた。控え目な笑顔に少しいたずらっぽい色が見えて微笑ましい。
「オーケー」と僕は答えて現地のお札を出した。お金を受け取り、ビニル袋に商品を入れて、手渡してくれたときの彼女の照れたような表情がかわいらしかった。(後で日本円に換算したらえらく安かった)。
とても気持ちのいい買い物だった。
最終日の昼、連日の暑さと歩き疲れで「トゥクトゥク」を利用した。いわゆるタクシーなのだが、車ではなくバイクに荷台が付いた乗り物だ。軽トラの荷台に乗っているとイメージしてもらえたらわかりやすいだろう。
外の風を感じながら走る「トゥクトゥク」は、これがなかなか気持ち良い。思わず顔がほころぶような気持ち良さだ。風に吹かれながらぼんやり通りを眺めていると、旅行で来ているのだろう白人の女性が、頬を真っ赤にして自転車を漕いでいた。
気分が良かったからか、彼女の自転車を追い抜くときに僕は思わず「keep on Going!」と声をかけていた。
僕の声に気付いた女性は、「もう限界よ!」という思いっ切りしかめた顔を作り(欧米人のああいうユーモアがとても好きだ)僕を笑わせてくれた。遠ざかりながら「bye!」とお互い声を掛け合って、数秒後には彼女の姿は見えなくなった。
一瞬のやりとりだった。それでも今振り返りながら不思議と胸にこみ上げてくるものがある。なぜだろう。
とまぁ、旅の参考には一切ならないことをつらつらと書き連ねてしまった。しかし旅から帰ってきて2週間が経ち、思い浮かぶ光景を正直に書いたつもりだ。
ラオスのきれいな夕焼けや、ヨーロッパを感じさせるお洒落なカフェ、美味しい現地の料理やビールなど、ガイドブックに載るような、旅たらしめる体験はあったけど、振り返って思い返すのは、こんな些細なシーンややりとりだったりする。
おそらくその場で会った人たちとは金輪際会うことはない。心が通ったとも思えない。言葉さえ通じないのだ。それでもそんな小さな心の交流が、心地よく記憶に居座っている。
ラオスに限らず、旅はいつでもそうなのだ。
旅から帰ってきて3日後に、仕事で京都に行った。
朝から予定詰めの一日で、18時過ぎにようやく解放され、心地いい気怠さを伴って新幹線に乗るため駅の改札をくぐろうとしたときのことだ。
ふと改札の横の光景が視界に入る。
20歳くらいの、スーツケースを脇に置いた外国の女性が今にも泣き出しそうな表情で日本人の女の子と向き合っていた。
「あ、泣くな」と思ったのも束の間、ついに彼女は声を上げて泣きはじめ、腕を拡げ日本人の女の子にハグをした。
日本人の表情はこちらからは見えなかったけれど、おそらく彼女も泣いていたのだろう。ふたりの親密なハグがそれを物語っていた。
ふたりはただ、別れを惜しんでいた。
きっとあの外国の女性は、日本のニュースを目にしたり、SNSで日本のことを知る度に、その日本人の女性の顔が浮かぶんだろうなぁと、そんなことを思っていたら、突然僕の胸を込み上げてきた。込み上げるというより突き上げるという表現の方が近いかもしれない。あまりにも突然のことで抗うことができず、気付けば僕も涙を流していた。
彼女たちの間にある何が僕に涙を流させたのか。それは正直まだ分かっていない。
ただ今こうしてラオスの旅で思い出したシーンを並べてみて、少しだけわかってきたことがある。
僕らは好むと好まざるに関わらず、年齢を重ねるほど、自ら決めて声を掛け合って別れることが少なくなってくる。
連絡が途絶え自然と疎遠になることや、突然の(もしくは予期された)死によって別れることが増えてくる。雑踏の中に消えていく相手の背中が見えなくなるのを、ただ茫然と立ちすくみながら目で追うような別れだ。そこにはいつも寂しさが伴う。
けれど「さよなら」と声を掛け合って(あるいはハグをして)、「せーの」で足を踏み出し別れることはそれとは違う。一時の寂しさはあれど、とても清々しいのだ。
清々しい別れの代表が卒業式だ。入学時に決められた数年後の別れがあるからこそ、出会いは煌めき、別れは清々しいものになるのだ。そんな記憶は、振り返るときはいつも決まって僕をあたため、慰めてくれる。
旅という限られた時間の中では「こんにちは」と「さよなら」は常にセットだ。数秒後、数日後には「さよなら」が待っている。僕は僕の、彼らは彼らの日常に向かって「さよなら」をする。
その別れは、僕が生きる上で必要としているあたため慰めうる記憶として、いわば代替的に手渡してくれる。
それが(現時点における)僕が旅に出る理由であり、だから僕はまた旅に出ることになるのだと思う。「さよなら」をするために、旅に出るのだと思う。
文/写真:Takapi