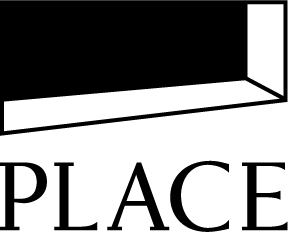ズーンと沈み込むような重さだった。
お盆を過ぎた頃、所用のため夕刻早めに在宅勤務を切り上げて、電車で数駅先まででかけた帰り道。21時をまわった世田谷線の駅の誰もいないベンチに腰掛けたとき、ベンチがまるでクッションのように硬質さを失い身体の重さに合わせて沈み込んでいくような感覚を覚えた。同時に身体全体にGがかかったような重さを感じた。そして抗えないような眠気が襲ってきた。
数10秒後に電車のアナウンスが鳴り、電車がホームに流れ込んできたのを合図に立ち上がろうとしても、腰を上げるのに手持ちのエネルギーをすべて絞り出すくらいの気概が必要だった。そのくらい重たかった。
「疲れたな」帰り道、家の近所の公園を横切る時にそう呟いていた。言葉にしてはじめて身体が、脳みそが、先ほど感じた重さが「疲れ」なのだと認識した。
疲れている。いや、もっと正確にいえば、身体の一部がずっと欠けているような感覚と言ったらいいのだろうか。筋肉・血液・その他身体を構成するパーツのひとつまたは複数の要素が減り続けている感覚だ。その要素は補充されぬままついにエマージェンシーをあげたとも言える。
補充されぬままの要素とは何か。おそらくここ半年の暮らしの変化によるものが大きい。そのくらいはわかる。

この半年で僕の暮らしは一変した。
朝早く起き満員電車に揺られる代わりに、朝はゆっくりと起き近所の公園を散歩し、気のすすまない対面の交渉ごとの代わりに、メールやslackで整頓された用件を伝え合意形成をはかり、空腹に耐えきれずお昼の定食のご飯を大盛りにする代わりに、昼は粗食にして午後3時にはコーヒーを淹れチョコレートを頬張り、雑談やら会議やらで仕事が捗らずに20時過ぎに会社を出る代わりに、19時にはあらかたの仕事を終え5キロほど近所をジョギングをしてシャワーを浴びてはビールを飲む暮らしになった。
効率化。
端的にいえばそうなのだろう。今の僕の暮らしは、これまで首を傾げながらも従ってきた「形式」からようやく解き放たれ、実に簡便にコトを進められるようになった。
エネルギー消費は確実に減っている。それなのに何かがずっと減り続けているような感覚がある。そしてそれはどうしようもない疲労感を伴っている。
マシーンのように効率化するだけでは人間はうまくいかないらしい。少なくとも僕はそうだ。「疲れ」についてもう少し考える必要がある。

これまでの人生で疲れていた頃を思い出して浮かんでくるのは、部活に明け暮れた高校生の頃と、右も左もわからない社会人なりたての頃だ。
陸上部だった僕は、毎朝5時に起き、ほぼ始発で電車に乗り込んでは学校に着くなり朝練をこなし、昼休みはトレーニングルームで筋トレ、放課後はみっちりと日が暮れるまで練習をする生活を送っていた。
これだけの練習量をこなせば当然帰宅後は何もする気が起きず、ご飯を食べ風呂に入ったらサッと勉強を済ませて(あるいは翌日に回して)すぐに寝るような生活だった。
今こうして振り返りながらも、あの練習量に耐えられたなと思うけれど、日々の練習で疲れきった身体も、翌朝になればほどよい筋肉痛を伴って、むしろエネルギーに満ちていた。早朝学校に着いた時には早く走りたくて仕方がなかった。
ひとつ思い出せるルールがある。それは特に練習を追い込んだ翌日に必ずやらされていた、サッカーやバスケなど陸上競技とは関係のないスポーツをするというレクリエーションだ。「積極的休養」と言われたそれは、完全に何もしない休息を与えるよりも軽い運動をすることで回復を早めるというものだった。
休養という名の「別の刺激」を与えることで身体の調子を整えることを当たり前にやっていて、その頃それはとても機能した。身体を酷使する練習ではなく、ただ楽しむためだけの運動は、身体が喜ぶのかバキバキの筋肉痛でも不思議と身体が動いた。さらに言えば、「別の刺激」を受けて回復した身体は、ひとまわり大きく強くなったような気にさえなった。

新卒で入社した会社は、入社2日目に「飛び込み営業」をさせるような体育会系の現場だった。慣れない社会人のしきたりに戸惑いながら終電近くまで残る業務、おそらく今ならパワハラ認定されるであろう上司の「かわいがり」、毎朝8時には出社しなくてはいけないしきたり(毎朝6時に起きていた)、そんな日々の中にあって、疲れは溜まっていく一方だった。朝の電車でいかに立ちながら睡眠をとるかが目下の課題だった。
それでも夜10時になれば「終電まで」と会社をいそいそと出て飲み行ったり、月金まで働き疲れ切っているはずの土曜日の朝に、河原に集合してはバーベキューをするような活動ぶりだった。
今思えばだいぶ無茶な日々だ。ストレスフルな仕事とは真反対の「楽しい刺激」をわざと入れていれることで相殺していたような気がする。それは高校生の頃の「積極的休養」となんら変わらない本能的な回復方法だった。
どうやら、意識的にせよ無意識的にせよ、自身にかかった負荷はただじっと座して回復するのを待つのではなく、別の負荷をかけることで回復をするようなことがあるらしい。
かかる負荷に代替する負荷。生きていく上では双方が必要というわけだ。
まぁ。とはいえ「それは当時若かったからだろう?」と言われればその通りなのだけど。

夜の街はまだ少し気が引けるからと、8月末の週末の午前中に友人らとブランチをすることにした。朝からビールを出すお店で、ほどよくお酒も入り2時間程度よく笑って話せた会だった。ほろ酔いで解散し、酔い覚ましのためひとりで渋谷のカフェに入った。
椅子に深く腰掛け、アイスコーヒーを一口すすった時、ほどよい疲労感が全身を包んでいるのがわかった。それは頭から爪先まで均等に行き渡ったような疲れだった。その疲れが心地よくてそのまましばらく微睡んだ。目を閉じれば周囲のザワザワとした人の気配を感じる。それが不思議と気持ちがいい。僕が僕自身から開放されるような感覚があった。
目が覚めた時、どこか浮遊するような軽さが身体を纏っていた。先日の駅のホームで感じた重さとは真逆の感覚だった。そして全身に残った倦怠感とは裏腹に頭は冴えていた。伸びをひとつしたら、疲れが雲散霧消するような、そんな予感に満ちていた。エネルギーが充填されていた。
効率化した「やりとり」の負荷に代替するもの、それは手を伸ばせば触れる距離で友人知人と非効率な(そしてそのほとんどが馬鹿し合いの)話をすることだったり、街の営みに身を任せては、その場の空気に馴染んでみることだったり、そんな「人の気」なのかもしれない。
僕には人の気が足りなかった。
そのことがわかったら拍子抜けしたように安心した。
それは今はまだ徐々にでも、ふだんの暮らしで充填できるものだから。
陽の高い帰り道の中、はずむような足取りで帰途についた。
文・写真:Takapi