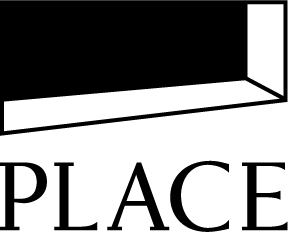いつものジムで軽く汗を流し、一息つこうとロビーで寛いでいたら、隣接しているスタジオから小気味いいビート音が流れ始めた。おそらくBTSだと思う(最近音楽に疎い)。その音楽に合わせて女性インストラクターの快活な声が響く。
「はい、◯◯のポーズ!」「腕を斜め上にー!」という声から察するにおそらくダンスレッスンだ。「なかなか合わないですねー」というインストラクターの言葉から、集団レッスンであることもわかる。「合わない」という割にその声から焦燥感のようなものは感じない。どことなく楽しそうですらある。きっと和気藹々とした初心者向けのレッスンなのだろう。
どんな人たちが受けているのだろうと少し興味が出て、帰り際チラッと覗いてみたら、少し禿げかかった白髪の初老のおじさんと目が合った。いや、正しくはレッスンスタジオに設置された鏡越しのおじさんと目が合った、ような気がしただけだった。彼はただ、鏡に映る自身の身体の動きを確認しながら一心不乱に手足を動かしていた。
まさか初老のおじさんがいると思わず、驚きとともにスタジオ全体に目を移せば、10名近い「おじさん」達が一所懸命に踊っていた。数秒程度の観察だが、彼らの表情はインスタラクターの醸す雰囲気とは裏腹に真剣そのものだった。
鬼気迫るようなおじさんの表情と、思うように動いていない(であろう)チグハグなダンスを見ていたら、なんとなく居心地が悪くなってしまって、足早にそこを後にした。
ジムを出て少し歩いていたらしてふいに込み上げるものがあった。急なことで一瞬たじろいだ。鼻の奥がツンとして少し目が潤みさえした。
なんだこれは?突発的な感情の波に溺れながらその出所を頭の中に求めた。でも探らずともほんとはわかっていた。
僕は感動したのだ。真剣な表情でチグハグなダンスしていたおじさん達に感動してしまったのだ。
その足で行きつけの洋食屋さんに入り、カウンターに座って、今しがた起きた感情について思いを巡らせてみた。
なぜ僕はあのおじさん達に感動したのか、いくら考えても理由がわからなかった。同情ではない、憐憫でもない、そういう類の感情ではないことはわかった。でもそれ以上いくら考えても理由が出てこなかった。
考えることを諦めて、ぼんやりとシェフの動きを目で追うことにした。この洋食屋のシェフの一片の無駄を許さない所作がとても好きなのだ。
このお店の名物はハンバーグ。半数以上の人がお昼時に注文をする。シェフは注文を受けると静かにフライパンに火を点し、バットから「タネ」を取り出すと、2度3度自身の両手でキャッチボールをしてそっとフライパンに載せる。載せたらその間にキッチンまわりやまな板を専用のふきんで拭く。一定の時間が立ったらフライパンに水を差し蓋をする。焼き上がる間にまたシンク周りをふきんで拭く。
そのひとつひとつの動作を見ていると、きっと数千回、ひょっと数万回と繰り返されてきた所作なんだろうということはわかる。それだけ一切無駄のない動きだ。一連の所作には厳格な雰囲気さえ漂う。なるほどシェフの持ち場は「聖域」と呼ばれる理由がわかる。シェフの面立ちにもそれは表れている。きれいな坊主頭に一筋の険しさが宿る表情はまるで修行僧だ。それでも料理ができあがればいつも慈愛に満ちた微笑みを浮かべて、太く穏やかな声で「お待たせしました」とカウンター越しに差し出してくれる。
言うまでもないが、ここで出されるハンバーグはとても美味い(前にも書いた気がする)。この日も夢中になって皿と向き合い、ものの数分で完食した。
水を一口飲み、ホッと一息入れてキッチンに目をやれば、数分前と寸分変わらない厳格な背中がフライパンと向き合っている。シンクやステンレスの壁は汚れひとつなく、それでいて新品とは違う使い古された親密な光を放っている。
「ごちそうさまです」大きな背中に頭を下げて席を立つ。勘定を済ませ店を出る時には「ありがとうございます」とシェフが背中に声をかけてくれる。
その声を背負ったまま店を後にした。みぞおちあたりが温かい。その温もりはきっと料理だけではないはずだ。
ここにもひとつの感動があった。
今年はこれまでになく感動を強要された夏だった。そして感動を疑った夏でもあった。
1年順延された祭典には、遅々として進まない感染症対策に対する市井の苛立ちを、「スポーツの感動」で覆い隠さんとするような狙いが見えてしまって、いざ祭典が始まっても、自身の感情に蓋をするように、画面越しのアスリートから目を逸らす日々が続いた。
そんなことだから、メダルをとった歓喜の声がテレビ越しやSNSのタイムラインに上がる度に、なんとも行き場のない感情とやり合う羽目にもなった。感動に尻込みする数週間だった。
本当ならもっと気安く感動したい。けれど「道具」にされた感動からは距離を置きたい。まわりの空気にも流されたくもない。なかなか難しい。考えすぎなのかもしれない。
翻って、先日のジムと洋食屋で感じた小さな感動は、湯船に浸かるような気分の良さがある。鼓舞するような強さはないけれど、ゆっくりと染み渡る滋養のような温かさがある。
感動なんて小さくたっていいし、誰に理解されなくてもいい。
身体の器官なのか、頼りない心なのかはわからないけれど、「自分自身の中を通った感動」だけは僕自身がしっかりと把握してあげたいし、できるだけ手放さずにいたい。
文・写真:Takapi