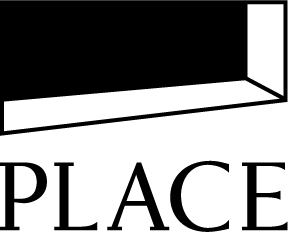昨年末からなかなかバタバタとしている。理由はハッキリしていて、本業の方でこれまで数年かけてやってきたことをまとめるような仕事(詳細は伝えられないのだけど)が突如降ってきて、年末から年始にかけて急ピッチで行うことになったためである。
さながら棚卸のような作業で、ここ1ヶ月くらい、毎日のように記憶の引き出しを開けては(時に鍵がかかったり埃を被ったような引き出しもある)、やっていたことを引っ張り出して「現在にもフィットするものなのか」の品定めしている。品定めされた記憶は、新しく拵えられた大きな箱に整理整頓して敷き詰めなくてはならない。言い換えるなら引っ越しだ。部屋中のあらゆるクローゼットを開け放ち一旦荷物をすべて取り出し、新居に持っていくものと捨てるものに分別し、要るものだけ段ボールに詰め込んだら、そこから新居で荷解きをして、また新しい棚なりクローゼットなりに置き直すような作業に似ている。
やり始めの頃は途方にくれた。数年間やってきたことをざっと取り出すだけでも相当な数だ。目眩にも似たような感覚をかかえながら、年末年始のほとんどを近所のカフェにこもって、パソコンと睨めっこしながら過ごすことになった(早く浮かれたように酒を飲みたい)。
埃の被った引き出しを開く度にげんなりもした。数年前とは言え、やはり年月を経ていれば「ガラクタ」となるものはある(というかほとんどがそうだ)。そういうのを見つける度に、新居に持っていくのか、いっそ潔く捨てるべきなのか、ひととおり悩むことになる。そして大抵は「なぜ僕はこんなガラクタを作ってしまったのだろう?」と自問自答することにもなった。この自問自答の時間も結構ヘビーだ。コーヒーがますます苦くなる。
それでも、毎日のようにそんな作業を繰り返していたら、不思議とリズムが出てくるようで、あれだけうんうん唸りながら整理をしていたのが嘘みたいにサクサク進むようになった。いよいよ五合目を超えたあたりからは、徐々に楽しくすらなってきていた。引っ越しになぞらえるなら、新居に運び込まれ、部屋中を埋め尽くした段ボールが徐々に減っていき、畳まれた段ボールが部屋の片隅に積み上がっていくような気持ちよさに似ている。
棚卸の気持ちよさに酔っていたら、そういえば、と思い出すことがあった。
大学生の頃バイトしていた居酒屋では、定期的に「棚卸」の号令がかかり、その度に、指名されたメンバーであらゆる食材・酒・備品等の在庫チェックをさせられる機会があった。冷蔵庫の隅々までチェックしたり、普段は入らないような備品で敷き詰められた埃臭い部屋なんかに入り浸っては、渡された用紙と睨めっこしながら在庫数を書き込んでいく作業は、不思議と苦ではなかった。むしろ楽しかった。あの楽しさの正体はなんだろう?(いやもちろんたまらなく嫌いだという人もいると思うのだけれど)
過去を整理する棚卸と、居酒屋で行っていた棚卸に共通する楽しさは「際限がある」ということなのかもしれない。「ここまでやれば終わり」ということがわかっているものは、その終わりの爽快感を知っているが故、ゲームのようにこなせるのかもしれない。
と、ここまで理解して、新しい問いが浮かぶ。
棚卸を終えたら次はどうするんだっけ?
整頓されて空いたスペースは何で埋めればいいんだっけ?
年齢を重ねるほどわからなくなることはたくさんある。

先日、大学時代のサークルの先輩から「教えを乞いたい」と連絡が入り、小一時間朝食がてら話す機会があった。その先輩は、新卒でとある大手メディア企業に入社していて、同期の間でも憧れの的でもあった。卒業後も何度かお会いしていたけれど、学生の頃と寸分変わらず快活な様子(学生の頃からテキパキとしていて気持ちのいい人だった)で、社会人生活を謳歌しているように見えた。謳歌しているなんて言葉、滅多に使わないけれど、その言葉でしか言い表せないくらい、要は仕事をバリバリとこなし、私生活も充実している人に見えた。
数年ぶりに会った先輩は相変わらず快活だった(朝なのにすごい元気だった)。聞けば数年前に新卒で入社した企業は退職されていて、今はベンチャー企業で真新しいことに取り組んでいるとのこと。「新卒で入社した会社が好き過ぎちゃって、このままじゃいけない」そう思ったらしく、何か新しい挑戦をしなくてはと、なかば焦燥感に駆られて転職したということで、その前のめり感も含めて相変わらず小気味がよかった。
そしてベンチャーで働く傍ら、副業でも新しいチャレンジをしていて、その副業が、僕が本業でやっていることと近いということもあって、「教えてほしい」と声がかかったわけだ。
席につくなり、挨拶もそこそこに、彼女のスマホの中にリストアップされている質問事項を、上から順に答えることになった。答える度に、「へぇぇそうゆうことか!」「知らなかた、なるほどね!」などと歓声が上がる(そう、あれは歓声だった)。その間もずっと彼女の右手はスマホで僕の答えを打ち続けている。気づけばテーブルの上の朝食は冷めきっていて、ほぼ1時間ずっと、質問と答えの応酬を繰り返していた。そして一息ついて、時計を見るなり「ありがとう!」と席を立ち、会計を済ませて、挨拶もそこそこに颯爽と帰っていった。
彼女はきっと、十数年分の棚卸を終えて、スッキリした心持ちで、今新しい道を作らんと走り出しているんだ。早足で去っていく背中を見送りながらそんなことを思った。その後ろ姿は、清々しくも羨ましくもあった。

大なり小なり、人生の中では定期的に棚卸の時期はやってくる。それは自分で気付いて取り掛かることもあるし、外圧によって着手せざるを得ないこともある。そして、それは当然ながら痛みが伴う作業でもある。でもたぶん、遅かれ早かれ、手をつけなくてはいけない時期というのはあって、そのタイミングは逃してはいけないんだと思う。この年齢になって、なんとなくそれだけはわかってきたようにも思う。
年末年始の棚卸を振り返れば、過去に一緒に仕事をした人と対話をする機会でもあった。それは頭の中だけで完結することもあれば、具体的に声をかけて会話をすることもあった。いずれにせよその邂逅は僕自身をそっと温めてくれた。何かを成したわけではないけれど、人とのつながりは確かにあったんだと、そんな当たり前のことに気付くことは、小さな自信のような、勇気のようなものを与えてくれもした。そう考えると、棚卸の時間は苦痛だけでもないようだ。
学生時代の居酒屋の棚卸のご褒美は、そのあとの「発注タイム」だった。在庫が薄くなったものを注文機からポチポチとするのがこれまた楽しい時間だった。普段であれば注文しない物を選び注文するのは、なんだか悪いことをしているような、くすぐったい気持ち良さがあった(僕だけかもしれないけれど)。たぶん、人生における棚卸のあとのご褒美も同じようなことなのだと思う。
次に何を「発注」しようか。少しずつ考えていくことにしよう。
文・写真:Takapi