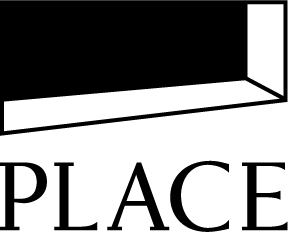先日仕事でご一緒したカメラマンさんは、個人的にその方のInstagramアカウントをフォローをしているくらいファンで、そんな方と仕事でご一緒できることにワクワクしていた。同時に「こんな仕事受けなきゃよかった」と思われないといいな、とか「怖い人だったらどうしよう」とか、若干の不安も脇に抱えながら、当日現場に向かうことになった。
実際にお会いすると、とても物腰の柔らかい方で、まずひとつの不安は解消された。撮影まで時間があり、待機場所で雑談がてら話していた時も、話し方がとてもチャーミングで場を和ませてくれた。
驚いたのは撮影が始まってからだ。突然何かのスイッチが入ったように縦横無尽に現場を動き回り、撮影対象者にカメラを向けながら「いいね!」「あぁ、最高!」と声を張り上げながらシャッターを切り始める。時折髪をかきむしり少し思案したかと思うと、「じゃあ次はこの姿勢をしてみよう」とかアイデアが飛び出す。その一連の所作はまるでエレファントカシマシの宮本さんのようで(ちなみに女性である)、場の空気もそのテンションにつられて上気していく。それは脇で見ていた僕自身がじんわりと汗をかくくらい、実感としてわかるほどで、もはやライブだった。撮影される側はふだん撮影の機会などないいち会社員。撮影なんて慣れてないはずなのに、だんだんとまんざらでもないような気になっている雰囲気が表情からわかる。撮影された写真はすぐにPC画面に転送されていて、その写真を見れば鳥肌が立つほど「いい瞬間」を切り取っている。僕は、ただ「すごい」とつぶやき立ち尽くすだけだった。
撮影が終われば、それまでの勢いが嘘のように一瞬で元の物腰のやわらかい方に戻った。その一連の動きがとても自然でまったく無理がない。息切れもしていないし疲れも見えない。撮影されていた方も自然と撮影前の雰囲気に戻る。きっとこれは何百回、何千回と繰り返し現場に立ち続けないと身につかない熟練の所作なのだと思った。プロだ、と思った。

そんなことを思っていたら、そういえば、と数年前に参加した友人の結婚式の司会者を思い出した。その司会者の年齢はきっともう還暦に近い。タキシードを着て蝶ネクタイをしてきっちり七三に分けた髪型。その姿はあまりにも「昭和的」で、場違いの空気をふんだんにまとっていた。なんだか冗長な話をし出しそうな雰囲気すらあった。
それが一言、たった一言だ。ひとつ言葉をマイクを通じて放っただけで、披露宴に参加した浮き足だった若人全員の視線と耳がその人に「もっていかれる」のがハッキリとわかった(今となってはどんな言葉だったかは思い出せない)。その後の回しっぷりは説明の必要がない。気づけば僕は司会者に駆け寄り一緒に写真を撮ってもらっていた。ものの1時間程度でファンになってしまっていたわけだ。
後で聞けば、その司会者は業界では有名な方だったらしい。同じように彼の「回し」を体験し、僕と同じように「持っていかれた」人が多数いたようだった。その方も紛れもなくプロだった。
たまにそういうプロに出会うと、嬉しい反面自身の至らなさにすっかり自信をなくしてしまいそうになる。どうしてもそこには熟練と呼ぶだけの相当数の現場を想像してしまうからだ。その胆力も耐力もアドレナリンも僕にはありそうにない。とはいえ、そんな方々にもはじめての撮影もはじめての司会もあるわけで、きっと多くの失敗や気づきを繰り返して、今僕が目の当たりにしている「プロ」になっていったのだろう。そんなことはわかっていても、いや、わかるが故にやはり「はぁ、すごい」とため息混じりに背中を眺めてしまう。
何歳になってもプロという言葉には弱いようだ。

今住んでいる家は築古マンションで、大掛かりなリノベーションはしたものの窓がガタついていて、冬は寒いし、夏は暑い。窓を変えたいのだけど可能かどうか、マンションの規約を見ても判然としない。
僕の姉の旦那さんが不動産会社で働いていることもあって、先日我が家に遊びに来た際に、藁にもすがる気持ちで相談を持ちかけた。途端、「では利用規約を見せてもらってもいいかしら?」と何かのスイッチが入ったようにテキパキとしだした(普段がのんびりしているわけではない)。渡した利用規約をパラパラと見ては、「あの情報はありますか?」「なるほど、そういうことですか」と完全に口調も仕事モードに入っていた。ものの数分で一通りわかったのか、いくつもアドバイスをくれた。一通り話し終えて利用規約をパタンと閉じた瞬間、ふだんのお義兄さんの顔に戻っていた。
ここにもプロがいた。
そして思った。ひょっとしてプロになるのは「スイッチ」ひとつなのではないか、と。
そう考えれば、いつも通っている鮮魚屋さんも、コーヒー屋さんも、バルのオーナーも、ふだん仕事を一緒にしている同僚や上司も、見慣れ過ぎていてその「スイッチ」が入る瞬間を見逃しているだけで、みんなそれぞれプロのスイッチを持っているのではないだろうか。
僕にしても、たまの講演の機会で話す時には、わかりやすくスイッチを入れているではないか。「さて」と声に出すようにアドレナリンを放出する瞬間は、振り返れば結構な頻度である(本当にアドレナリンが出ているかはわからないけれど)。スイッチの大小はあるかもしれないけれど、僕らはちゃんとスイッチを持っている。あとは、そのスイッチを押すだけなのだ。たぶん。
中年に差し掛かる年齢と言えど、そのスイッチはまだあるはずだ。
錆び付いてスイッチが押せなくなる前に、恥を覚悟でスイッチを押し続けていきたい。
押す機会がないなら、スイッチを押せる場所を探しにでかけよう。新緑の、いい季節になったことだし。
文・写真:Takapi