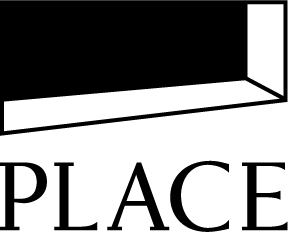毎年1月2日と3日は、箱根駅伝がスタートする時間くらいに起き、テレビを点けながら、おせちをつまみつつ酒をチビチビとやるのが、なんとなくの恒例となっている。
箱根駅伝においては古豪と呼ばれる大学の付属高校の陸上部出身ということもあり(短距離だったけれど)、なんだかんだと母校の順位をずっと追いかけては一喜一憂してしまう。ここ数年はシード落ちが当たり前になる程苦しい状況だったから、復路の後半になるとテレビを消してしまうこともあった。
今年はとても善戦していて、例年以上にテレビにかじりついていた。最終走者に襷が渡った時には、正直もう優勝は難しいと思っていたが、それでも久々の上位入賞の期待で心が踊り、ゴールまで見届けようとテレビの前から離れずにいた。
復路の最終走者が大手町に戻ってきて、沿道を埋め尽くす観衆がテレビにわっと大写しになった時、ふいに込み上げるものがあり鼻の奥がツンとした。箱根駅伝に出場した経験を持つテレビの解説者も、観衆の多さと「拍手による声援」を目の当たりにして「これが箱根駅伝ですね」と上気していた(ような声の上擦りようだった)。その言葉に頷きながら僕はほんの少し泣いていた。
見ず知らずの人が誰かに声援を送る姿になぜここまで惹かれるのか。それはよくわからない。声援を送ることそのものに感動するかと言われると、きっとそういうことでもないのだろう。仮にその大学の応援団が、沿道を埋め尽くして声の限りに応援をしていても、同じような感情にはならなかったと思うから(それはそれで違う感動があるのだと思うけど)。
声援を送る側と送られる側は今後の人生でも交わることはない。要はその場限りの声援だ。でも、なにかそういうところに人の良い面を見ているような、もっと言えばそんな人の一面に救われるような気持ちにもなっていたのかもしれない。
結局のところ、自身の気持ちの高まりの正体はわからないまま、2位でゴールした母校の選手に、鼻をすすりながらテレビ越しに小さく拍手を送った。

心地よい感動に包まれながらテレビを消すと、10年以上前のホノルルマラソンを走った時のことを思い出した。
朝5時、まだ夜が明ける前にスタートし、ちょうど朝食時間帯に帰ってくるこのレースは、前半の暗い時間帯はほとんど応援がなく、中盤になってようやく沿道の応援が聞こえるようになる。ただ後半30キロ過ぎの陽が差し込んでくる時間帯が本当に苦しい。ちょうどその間は民家の横を走るような格好になるから、沿道で応援する人もまばらになってきて、余計心細くなったのを憶えている。
それでも、おそらく近所に住んでいる地元の方だろうか。フルーツを箱いっぱいに詰めて沿道に出しては、「食べていきな」と促しながら、満面の笑みで「keep on going!」と声をかけてくれるのだ。その声援は、疲れ果て膝を痛め泣きそうになっていた身にはとても嬉しかった。鼓舞するよりも慰撫するように僕の背中を押してくれた。結果として、そこからなんとか踏ん張り42.195kmを走り抜けることができた。
なんとものどかな光景だ。でも、ホノルルマラソンで憶えているのは、地元民が気楽な声援を送ってくれた景色なのだ。正直ゴールした瞬間はあんまり記憶にない(体力がギリギリ過ぎて記憶が飛んでいるのかもしれない)。
見知らぬ人の気軽な声援に救われることは、たしかにある。
そしてそれはスポーツでなくても。

娘ももう9ヶ月になり、徐々に外に出る機会が増えてきた。とは言えまだ慣れないことも多く、ベビーカーで電車に乗る時はいまだに少し緊張する。ネットニュースを見過ぎなのかもしれないが、乗客全員が迷惑に思っているのではないか、今すぐベビーカーを畳めと言われるのではないか、といういわば恐怖にも近い感情が湧き起こってくる。
先日娘を連れて電車に乗った時は、席はほとんど埋まっていたものの、立っている乗客はほとんどいなかった。入ったドアの反対側のドア前のスペースが空いていたので、ベビーカーをドア脇のスペース(ドア脇の手すりのあたり)に置くことにした。そうなると座席の一番端に座る人とベビーカーに座る娘が、ちょうど斜めに向き合うような格好になる。
その時その席に座っていたのは、ちょっとやんちゃそうな若い男性だった。ベビーカーに座る娘に気付いたその男性は、すぐに耳に突っ込んでいたイヤホンを取った。何か言われるのかと身構えたのも束の間「めっちゃかわいいっすねぇ」と破顔して話しかけてくれた。
その言葉をかけられた時、じんわりと目頭が温かくなっていくのを感じた。「ありがとうございます」となんとか答えては、「嬉しいねぇ」と娘に声をかけた。その後も、イヤホンを外したまま、娘に声をかけ続けてくれた。次の駅に着くアナウンスが車中に流れ「降りなきゃ」と立ち上がると、「あっ」と声を上げた。「すみません、なんか楽しく喋っちゃってましたけど、お席譲るべきでしたね」と罰の悪そうな顔をして謝っては、足早に駅を降りていった。
きっと彼とどこか街中で会っても「その時の彼」だとは気づかないだろう。彼もそれは同じだと思うし、彼の中でももう忘れ去られたひとつの出来事になっていることと思う。
でも確実に僕の中に彼の声は残っていて、そして時間が経ってもなおそっと温めてくれている。そしてその声やシーンは、これからもふとした瞬間に顔を出しては、僕の背中を慰撫するようにさすってくれるはずだ。
彼が気軽にかけてくれた声は、僕が勝手に受け取った声援になった。
忘れないようにしたい。そして僕も気軽な声援をかけられるような人になりたい。
文・写真:Takapi