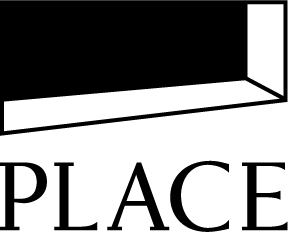仕事の関係で著書を出すことになった。長い社会人人生の中ではじめてのことだ。内容は専門的すぎるためここでは控えるが、端的に言えばここ数年やってきた仕事を振り返るような内容だ。ただ、数年前の仕事は、またその数年前の仕事につながっていたりして、結局のところ、執筆にあたってこれまでの社会人人生の棚卸を行うような格好になった。
僕はこれまで転職を2回経験しているが(現在3社目)、新卒で入社した会社は、中小の広告代理店。当然社名の認知も低かったから、「広告」というスマートな響きからほど遠い泥臭さがあって、入社2日目から単独で飛び込み営業をさせられるような、なかなかエキサイティングな環境だった。
そんな状態だから、人材教育やらマネジメントやらきれいなフレームとは無縁で、鞄持ちよろしく、先輩についていっては勝手に学び(先輩もノルマに追われ丁寧に教えている余裕がない)自分用にアレンジして実行してはコテンパンにされて(お客様にも先輩にも)、知らず知らずのうちに「仕事の筋力」がつくような、そんな強かな現場だったように思う。
年齢とともに知恵やノウハウは積まれていくものの、仕事に対する反射神経のような、基礎代謝のようなものは、若い頃に土台として形成されるような気がする。新卒で入社した会社でのこんな野生み溢れる仕事は、なんだかんだ言って、今の僕のベースを作ってくれている。そういった意味では今となれば感謝である。
それはそれとして、苛烈な環境は人の結びつきを強くするのか、あるいは単に若い人間が多かったからなのかはわからないが、社員同士の仲は良かったし、文字通り同じ釜の飯を食うような結びつきがあった。
だから、会社を去ってもう10年以上になっても、いまだに年齢の近い「悪友」たちとは、たまに連絡を取り合っては(と言ってもいつも声をかけてもらうのだが)集まり、あの頃の話を肴に大いに飲み会が盛り上がることになる。
若い頃の、ある意味むき出しの自分を知っているからか、飲み会となればダメなところも笑いながら言い合えるのも嬉しい。年始に数人で集まった際には、盛大にダメ出しをされてしまった。それがまた不思議と心地よかった。

著書がAmazon上で予約が開始され、SNSで告知すると、新卒で入社した会社のひとつ年下の後輩からこんなメールが届いた(意図は変えずに少し改変している)。
「たぶん、先輩は旧友と積極的に連絡をとりあう人じゃないから実感してないかもですが、古くから先輩の事を知る人達は、今回の件に驚いたり感動しているんですよ」
彼と「先輩・後輩」の間柄でいたのは、ほんの数年のことで(しかも年齢もひとつしか違わない)、もはや20年近く前のことだ。それにも関わらずいまだに「先輩」と呼ばれるのはなんだか照れ臭くて、思わず鼻がツンとして画面のキャプチャをとってしまった。
前述のような環境が故、彼にはほとんど何かを教えたという記憶はない。憶えていることがあるとすれば、何か指摘する度に負けん気の強さからか、食ってかかってくる実直な(多分に生意気な)視線だ。そんな彼が20年近く経ってもなお「先輩」と呼び、わざわざ丁寧にメールをくれること(実際の文面はもっと長かった)は、感謝でしかない。自分の人格にはさらさら自信がないが、人格者がやたらと周りに多いことは、数少ない僕の自慢でもある。
 著書の発売とともに「若い頃」に再会する機会に恵まれたものの、年齢を重ねるほど仕事と向き合う中で「ひとり」だと感じるようにもなった。いや、実際には仕事の関係者は年齢とともに増えているのだが、仕事の重心が「判断する」ことに移るにつれ、伴ってどうしようもなく「ひとり」だと感じることが増えたということだ。おそらくこれは仕事だけの話ではないのだろう。
著書の発売とともに「若い頃」に再会する機会に恵まれたものの、年齢を重ねるほど仕事と向き合う中で「ひとり」だと感じるようにもなった。いや、実際には仕事の関係者は年齢とともに増えているのだが、仕事の重心が「判断する」ことに移るにつれ、伴ってどうしようもなく「ひとり」だと感じることが増えたということだ。おそらくこれは仕事だけの話ではないのだろう。
若い頃の、横の人数(同年代)も多く、目上の方から目をかけてもらったり、怒られたり教わったりすることによる「つながり」のようなものは、年齢とともに必然的に薄れていく。要はどんどん仕事が「自分次第」になっていくということなのだが、そうなると何かに迷ったり悩んだりすると、教えてもらったり相談するのを他人に求めずに、もっぱら「過去の自分」に聞く、ということになる。
その時に顔を出すのが、自身の基盤をつくったがむしゃらな若い頃だったりする。
若いうちの苦労は買ってでもしろ。
この言葉自体のもつ、多分に前時代的な精神論には目を逸らしたくなるが(それ故最近はめっきり聞かなくなった)、現実的な問題として、年齢とともに「自分次第」であることが増える分、「過去の自分」が解決策の一助なることはある。
そんな時、過去の自分を知っている人との再会が、思いがけずいい方向にアシストをしてくれることもある。それは長い人生における「拠り所」と同義だ。
今年もそんな拠り所に存分に甘えていく所存だ。
文・写真:Takapi