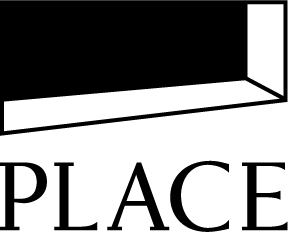娘がはじめて靴を履いて歩くことができた。
靴を買ったのはもう数ヶ月前で、何度か家の中で履かせようとチャレンジしたものの、履かせようとする度に号泣するものだから、その度に「ごめんごめん」と言いながら脱がせていた。とは言え、娘は娘で靴は気になる様子ではあって、玄関にある僕のスニーカーに足を突っ込んでは「んー!」と何やら要求し続けているような日々が続いていた。
このままではいけないと、いよいよ心を鬼にして「今日こそ履かせよう」と意気込んだ先月のとある休日。相変わらず泣き叫ぶ娘に「大丈夫、大丈夫」と声をかけ続けながら、まずは靴を履かせるところまでいった。ただ、なんとか履かせることには成功はしても、すぐに尻餅をついて身体をよじって脱ぎたがる。しかしここで引き下がるわけにはいかない。家の中にいるから歩けないのかもしれないと、そのまま娘を持ち上げてマンションの廊下に出ることにした。
廊下にはちょうどよく娘が掴まれる高さの手すりがある。その手すりに掴まらせてみると(その間もずっと泣いている)掴まれるものがある安心感からか、座り込まずに、まずは立つことができた。
ただ、立つことはできたものの、そこから微動だにできない。娘の少し前に立ち、「ほら、こうするんだよ」と言いながら足踏みをしてみる。ダメだ。じっと立ったままだ。「おいで」と目線の合う高さまで腰を屈め、できうる限りの笑顔をつくり娘を鼓舞してみる。ダメだ。じっと立ったままだ。思案してみたもののなす術なく、とりあえずそのままの格好で待ってみることにした(若干の投げやりな気持ちもあった)。
そこでひとつのことに気付いた。じっと立ったままの娘は、いつの間にか泣き止んでいたのだ。その表情に若干の好奇心のようなものが見えた。大人で言うところにニヤリといったような、そんな表情だ。「もしかしたらいけるかもしれない」と、期待を込めてもう少し待ってみることにした。
時間にして数十秒くらいだろうか(体感的には30分くらいに感じたけれど)、ついに足をジリジリと動かし始めた。そんな風に片足ずつ足を徐々に動かしてみて、足が思うように動くことを確認できたのか、ついに手すりから手を離し、ぎこちなくともしっかりと数歩歩いては、腰を屈めて待つ僕の胸まで真っ直ぐやってきた。
大盛り上がりの親をよそに(急いでカメラを用意して動画・写真撮影に忙しい)、娘は少しずつ歩数を増やせるようになっている。近くの壁まで歩き着き、壁に身体を預けるようにして、小休止した娘の顔は、たしかに笑っていた。「やった!」と破顔するような笑顔ではなく、「へへへ」とどこか得意気を含んだような、いたずらが成功した時のような、もっと面白がってやろうという気持ちが滲んだような笑顔だった(ように思う)。
そんな娘とは対照的に、僕ら親は破顔するように喜び勇み、少しだけ目尻に涙が浮かんでいたけれど。

はじめて何かができた時の、あのニヤリにも近いような笑顔を、ここ最近の僕はしたことがあったか、しばし振り返ってみたけれど、なかなか思い至らなかった。
浮かぶものと言えば、事前に調べずに己の勘で買ったクラフトビールが想像以上に美味しかった時とか、口コミを見ずにたまたま入った食事処が思いのほか美味しかった時とか、そういう時のニヤリしか思い返せない(なんてスケールの小さい話だ)。
そもそも学校という「社会」に放り込まれた時から、「何かができる」のそばには「誰かと比較して」がセットになっていることに気付いた。
かけっこが楽しくなってきた時には、徒競走というひとりだけが切ることができるゴールテープが用意されたし、学ぶことが楽しくなってきた時にも、テストという点数だけで優劣が測れるような仕組みが当然になっていた。
結果として、誰かよりも秀でることになれば、爆発的な笑顔を本人も(周りも)引き起こすことになるけれど(甲子園のあの盛り上がりを見れば一目瞭然)、反面、劣っているという「その他大勢」に組み込まれることを受け入れなくてはいけない、という現実もある。
「できた」のニヤリは、思いの外短く儚いものだったりする。そう思うとなんだか少し寂しい。

そんなことを考えていたら、今年はじめて本を出した時を思い出した。
脱稿した時にニヤリとできたかは思い出せないけれど(とりあえず書き終えた安心感と若干の徒労感の方が勝っていた)、本を出した後には、多くの友人・知人が嬉々として声をかけてくれた。その人たちの表情や言葉に触れて、嬉しい気持ちとともに、ようやく少しずつ達成感が湧き上がってきた。じんわりと。
「自分だけの達成」は、自分ではうまく達成に気づけずに、案外周りからの声で気付くようなことはあるようだ。誰かと比較しない黙々とした作業は、誰かの目に留まり、声をかけられた時にはじめて、いつの間にか自分が一歩進んでいるということを教えてくれる。
その掛け声はまた、「さらにもう一歩踏み出せるかもしれない」と調子づけてもくれる。そう考えると、ひとつの達成は、ゴールでもあると同時にスタートでもあって、周りからかけられる声は、次のゴールに向けた「号砲」と捉えることもできる。
ひょっとしたら、はじめて靴を履いて歩いた時の娘の「へへへ」の表情の奥には、僕や妻の幾分大袈裟な掛け声に乗せられているような気持ちがあったのかもしれない(ほんとのところはわからないけれど)。
これから娘は数多くの「はじめて」に挑戦していくことになる。なにかひとつできる度に、できる限り、大袈裟にでも喜び、声をかけ続けていこうと思う。
そしてそれはもちろん、近しい人たちにも。
文・写真:Takapi