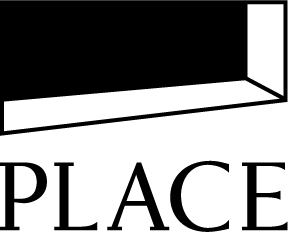ゴジラ映画の最新シリーズを観た。先月あたりから予告編がやたらとYoutubeで流れてきたのもあるが、なぜか繰り返しクリックしてしまうほど引き込まれるものがあって、公開初日に観に行くことになった。
思い返せば、ここ最近観た映画はどうも子どもの頃に夢中になっていたものが多いような気がする。『SLAM DUNK』もそうだし『シン・ウルトラマン』もそうだ。エンタメ業界のマーケティング的な戦略でそうなっているのか、単に僕の興味が枯れてしまったのかわからないけれど、どうやら「自分的リバイバル」が流行っているようだ。
ついこの間も、ふと子どもの頃に途中まで読みかけてやめていた野球漫画のことを思い出してしまい(野球少年だった)、どうしても続きが読みたくなって、amazonで大人買いをしてしまった(結果としてそんなに面白くはなかった)。
いつか見たものを改めて見たくなるこの現象について、同年代の友人と話していたら、彼は来年中学生に上がるお子さんがいるそうで、最近では彼が当時見ていた漫画や小説を子どもと一緒に楽しんでいるとのこと。当時の自身の感想をなぞるような言葉を子どもから聞いたり(まったく違う感想を言われたり)するのが楽しいようで、たしかにそれは楽しそうだと思った。
僕が影響を受けた作家の小説を読んで娘がどんな反応を示すのだろうか。その偏った趣味に辟易されるのか。ひとつ楽しみが増えた。

母親が50年前に働いていたというとある施設が、今僕が住んでいる場所の近所(と言っても数駅あるのだが)とのことで、娘の散歩がてら、母親を連れて行ってみることにした。
その施設の最寄り駅も、改修はされているものの50年前のまま残っているような箇所があったり、駅から施設に向かう道なりも並ぶ建物は変わったものの当時の面影が存分に残っていたりで、「あの時のままだわ…」とひとしきり感傷しきりであった。実際の施設は名前こそ残っているもののすべて建て直しされていて、一切の面影がなく途端に興醒めしていたけれど。
大人になるほどに、思い出の場所に出掛けたくなる理由はなんだろう。僕はといえば、中学生の遠足で鎌倉に行った時に入ったトンカツ屋が忘れられなくて(とにかく美味しかったのだ)、大人になってから友人を誘って探しに出掛けたこともあった。当時の思い出を紐解きながら(店名を忘れていた)、小一時間歩いて見つけた時の心持ちはなんとも言えないものだった(肝心の味は舌が大人になったのか感動はできずに余計なんとも言えない気持ちになったのだが)。

娘が通う保育園への道中には、地下に潜る線路のトンネルの真上を通る箇所がある。高台になっているその場所は、小さな公園もあって、西に走る線路の線上には当然ながら遮るような建物はなく、とても見晴らしがいい。空気が澄んでいると遠くに富士山を臨むことができる。
朝せっせと自転車を漕ぎながら雪を被った富士山を見ると、スッと背筋が伸びるような気持ちになるし、夕刻のくたびれた帰り道に、赤く染まった空に富士山のシルエットが見えるのは、さながら一日の終わりのご褒美のようだ。寒い季節の保育園の送り迎えに幾分怯んでいたが、これでひとつの楽しみができた。
今年一番の冷え込んだ朝、いつもの場所で富士山が目に入った瞬間、遠い昔の記憶がフラッシュバックした。それはマンションの6階に住んでいた小学校から中学生の頃だ。そのマンションの廊下も同じように空気が澄んでくる季節になると富士山が綺麗に見えた。そんな富士山を数秒拝んでから学校に通うのが日課になっていた時期が数年間ほどあったことを思い出した。当時なぜそんな願掛けのようなものをしていたのか、理由はわからない。思春期特有の悩みを抱える時期に、富士山のように”大きく揺るがないもの”は格好の拠り所だったのだろうか。
今富士山を見ている場所から、特急の電車で1時間程度西に行くと、当時住んでいたマンションがある格好だ。数十年経ち、場所は違えど、同じものを同じ方向から見ていることになる。そのことがきっとフラッシュバックを起こさせたのだろう。
あの頃と同じものを見ているという事実と、僕が子どもの頃見ていた景色を娘も見ているという事実に、少し狼狽えた。そして、朝の凛とした空気を吸い込んだからか、鼻の奥がツンとした。
きっと、何百万、何千万という人が(あるいはもっと多くの人が)同じように、いつかの自分の見た景色に邂逅しながら、こんな風になんとも言えない気持ちになっているのだろう。そう思うと、自分自身がなんだか大きな歴史に組み込まれた小さな小さな歯車になったような感覚にもなるから不思議だ。でも、そんなことにほっとしている自分もいた。
この感情を説明するのは難しい。
ちょうどよく、自転車を漕ぎながら頭に流れた曲に託して終わることにする。
ぼくらが昔見た星と
ぼくらが今見る星と
なんにも変わりがないそれが嬉しい
『嘲笑』ビートたけし
文・写真:Takapi