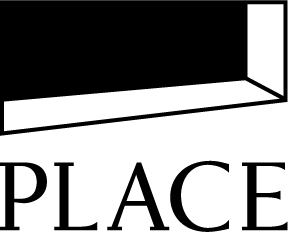大人になってからできた友人4人で数ヶ月ぶりに飲みに出かけた。仕事内容も業界も年齢もバラバラな4人だが、かえって気が楽なのか、定期的に飲むようになってもうしばらく経つ。
集まれば、大抵は仕事の話か(お金の話もついてまわる)、ペットの話か、健康の話をしている。最近では、集まるごとに徐々に健康の話の割合が増えている気がする。
先日も健康マニアの友人が勧めるサプリメントの話が中心だった。友人が告げる横文字のサプリメント名を何度か聞き返しながら、その場の全員がスマホでメモしていたのが、なんだかシュールで面白かった。
健康の話は言ってしまえば「将来を見込んで」の話だ。仕事の話をしても、今興味がある仕事や職場の不満よりも、10年後かそれ以上先を見越しながら、逆算的に「今どう立ち振る舞うか」という話に終始することが多くなった。
年齢を重ねてくると、積み重ねた経験から導かれる将来像を描く楽しさがある。引き換えに足元に転がる真新しいことへの関心が薄まってしまうことはたしかだ。それはそれで寂しいような気もするが、見渡せるものが広くなった分、小さなことに拘泥もしなくなった。要はだんだん気楽になっているのだ(ひょっとして、ベテランのサラリーマンが動じないのは、リーダーとしての責任でも意志でもなく、単に気に留めなくなったからなのではないか)。
一方で多くの会社の働く現場に目を移せば、「will」つまりはその人なりの「将来像」を、あらゆる社員に描かせ言語化させることを課すことが流行っているらしい。
先行きの見えない時代における焦りなのか、企業にとって都合のいい価値観を植え付けるつもりなのかわからないが、若い世代も年配も一様に「未来にどんな仕事をして、どんな風に社会に(会社に)貢献をしている人になりたいか?」を聞くようになっている。
「willハラ(ハラスメント)」なんて言葉も出始めているそうだ。ご多分に漏れず、自身の職場も同じような空気になっている。
今の年齢になってようやく、自身の可能性に見切りがつき、視野が狭まり、将来に焦点が合うようになった僕くらいの年齢に聞くならわかる。そうではなく、どんな可能性があるかもわからない、むしろその可能性がどこかに転がってるんじゃないかと躍起になっている若い世代に、まるで人生には一本筋の通った道筋があるかのように思い込ませ、未来を考えることを押し付けるのは、なんとも歪なものを感じてしまう。
ともすれば、前世代が溜め込んだここ数十年の「負債」を、一見きれいに見える「未来」を隠れ蓑にして、ただ若い世代に押し付けてるだけなのではと勘繰ってすらしてしまう。
ある程度経験を積んだ中年男性としてできることがあるとすれば、とにかく次の世代の邪魔をしないことでしかない。そう思っているのは、若い頃に「あれをやりたい」「これもやりたい」と言っては、我慢強く後押ししてくれた先輩がいたからだ。最近は彼らの顔を思い出すことが増えた。
彼らは一様に「それは面白いのか?」と聞いてきた。面白いならやれと、迷いもなく背中を押してくれた。できることなら僕もそうでありたい。
「未来どうありたいか?」ではなく「今面白いか?」を聞ける大人でいたい。足元に広がる「面白い」が積み重なった先に「未来」が手元にやってくるようになる。はずだ。

そろそろ2歳になる娘の最近の流行りはダンゴムシを探すことだ。
先日もいつもの公園に行くと、真っ先に桜の木に向かい、足元に転がる枝を拾っては近くの土をこねくり回し始めた。
ダンゴムシを探すことはもちろん、土の地面に触れる機会すらほとんどなくなってしまった身としては、懐かしいを通り越してフレッシュな気持ちになる。娘と一緒に桜の木の下にしゃがみ込み、土いじりを楽しむことにした。
娘に倣い、小枝を拾って土を掘ってみると、サラサラとした砂や粘土質のある土、濃い茶色から黄土色のような土色があって、なんだか楽しい。土に触れるうちに徐々に数十年前の子どもの頃を思い出してきたのか「石の下にダンゴムシはいたりするんだよ」などと得意げになっては石をひっくり返したりもした(結局見つけられなかった)。
夢中になって土をいじっていたら「ワンワン!」と、少し先から娘の嬌声が聞こえる。近くを通りかかった犬に気づいた娘は、早々にダンゴムシ探しを切り上げ、犬の方に駆け寄っていったらしい。
数秒間の犬との戯れが終わり、またダンゴムシ探しに勤しむのかと思ったら、今度は「シュー!」と言い出し、公園内にある滑り台の方に小走りに向かい始めた(シューっと滑るから「シュー」と呼ぶ)。滑り台は先月まで娘の中で流行っていた遊びだ。
娘の気まぐれな集中力と溢れんばかりの好奇心が羨ましくなりながら、手も繋がずひとり先を歩く娘の背を追いかけた。追いかけながら先日の取材のことを思い出した。

先日の取材は甲府の自然豊かな場所だった。
取材が終わり、山道を歩いていたら、お腹がオレンジ色の鳥を見かけた。大きさはスズメよりは大きく、ムクドリよりは小さいくらい。都会ではなかなか見かけない種類だが、子どもの頃図鑑で見たことのある鳥だ。思わず気持ちが昂る。
小学生高学年の頃、なぜか鳥にはまり、毎日鳥の図鑑を眺めたり、スケッチブックを買っては、写真を見て写生したりしていた。ついたあだ名は「鳥博士」。
さっき見かけたオレンジの鳥も確かにその頃に図鑑越しで見ていて、スケッチブックに描いた鳥のひとつだった。数分逡巡して頭の中から名前を導き出せず、ネット検索して、その鳥が「ジョウビタキ」だとわかった(少し寂しい)。
数年一緒に仕事をしている取材陣に鳥の名前を興奮気味に伝えれば、反応は至って素っ気ない。当然ながら誰もが鳥に興味があるわけではない。でも僕の興奮した様子が気になったらしく、なぜ鳥にそんなに舞い上がるのか理由を聞かれたので、小学生の頃の「鳥博士」の話をしたら、「まだまだわからないことがありますね」と笑われた。でも、なんだかそれが少し嬉しかった。
どんなものでも一心不乱にのめり込んだものは、時間を経てもなお身体のどこかに居座っていて、いつでも外に出たくてウズウズしている。たまに顔を出した時の開放感と、他人に自身の一端を知ってもらう喜びで、なんとなく気持ちがいいのだ。
そんなことで、ふだん見向きもしない自分自身に少しだけ愛着が湧いたりもするのだ。
そんなことを思い出しては、ふふっと笑いたくなるような気持ちを小さくこらえ、滑り台に向かう娘の背中を眺めながら「いいぞ、もっと行け」と小さく声をかけた。
文・写真:Takapi