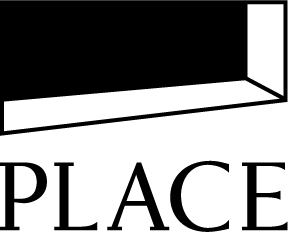あれはたぶん二日酔いの、よく晴れた日だったように思う。
午前中は自宅で働き、昼前に家を出て電車に乗った。座れるほどではないが、満員というわけでもない。平日の昼特有の、なんとも間延びしたような空気が電車内に漂っていた。
前日の酒量を呪いつつお腹をさすりながら(大体酒の次の日はお腹が弱い)、窓の外の陽の眩しさに耐えられず、かといって頭が働くわけでもなく、気晴らし程度にスマホで漫画を読むことにした。
頼りない体調のせいで電車の揺れのはずみで若干よろめいたのか、隣に立っていたおじいさんに寄りかかってしまった。と思ったら違った。おじいさんの方が寄りかかってきたのだ。あら?と思う間もなく、そのままおじいさんは倒れてしまった。バタンと倒れるというより、もう我慢ができなくてゆっくりと横になってしまった、という感じだった。
のんびりした電車の中の空気が瞬時に一変して緊張感に包まれる。座っている人が咄嗟に中腰になったり、「あっ」とか「えっ」とか、小さな声をあげる人もいる。
とはいえ、僕の足元で倒れた格好だから、とりあえず僕が「役回り」なのだと判断した。腰を落とし、なるべくおじいさんの耳元に近づいて「大丈夫ですか?」と声をかける。
幸いにもおじいさんは意識があり、「ああ」と小さく声が出た。ただ顔面蒼白だ。こりゃ立てないだろうな、と感じ取り、とりあえずその場に座らせることにした。
その場に座らせたものの、このおじいさんの体調がすぐによくなるわけではない。どうしたものかと考えあぐねていると、近くに座ってた数人が席を譲りだした。ただ、この状況から一度立ち上がって席に座ることはなんとも難しそうに感じた。そんな中電車内のアナウンスが流れ、間もなく駅に着くことを知らせる。
さてどうしたものか?と周りをキョロキョロしたところに、「降ろした方がいいよ」と3つくらい先の席からおじさんのアドバイスが聞こえる。
そうだよな、そうした方が良いよな、とは思ったものの、相手は自ら立ち上がれないおじいさんだ。毎日抱っこしている娘とは違う。ひとりで持ち上げて駅で降ろすというのは難しい。実際に肩に手をかけたが、瞬時に無理だとわかった。
「ちょっとどなたか…」と言いかけたところに、観光客らしい屈強な外国の若者の腕が伸びてきた。その若者は軽々とおじいさんを持ち上げ立たせることができた。その若者と一緒におじいさんの肩をかつぎ、ホームへ降りた。観光客は4人くらいで来ていたのか、全員が一緒に降りてきてくれることになった。なんとも心強い。
ホームに降りて、おじいさんの顔を改めて見れば、さっきよりは意識がハッキリしてきていることがわかる。ただなんとか立てているような状況だ。さて降ろしたもののどうすべきか?そうだ駅員だ。と瞬間的に脳内でひとりQ&Aをし、駅員を探す。50M先の方で歩いている駅員を見つける。屈強な若者におじいさんをお任せして駆け足で駅員のところへ向かう。駅員に声をかければ慣れた様子で、「担当呼んできますね」と改札の方に向かっていった。
また駆け足でおじいさんのところに行き、外国の若者には拙い英語で、駅員がもう来るから大丈夫、ありがとう、と伝えた。心なしか若者たちの顔に安堵の表情が浮かんでいるように見えた。
フラフラするおじいさんの肩を支え、「大丈夫ですよー。もうすぐですから」となんとも間の抜けた声をかけながら近くのベンチまで歩き、ゆっくりと座らせる。とりあえずここまでやれば大丈夫かと、ほっとしたところに、ビニール袋を持った若いサラリーマンが隣にいることに気付いた。「これ、その方が落とした薬かと」と手渡してくれる。ああ、ありがとうございます。と声をかける。若いサラリーマンは小さく会釈をすると足早にその場から去っていった。
1分くらい待って駅員さんがやってきた。さっと状況説明をして僕の役割も終了した。
おじいさんはまだ状況がよくわかっていない感じだったけれど、「お大事に」と声をかけた僕に対して「ああ。ありがとうね」と小さく微笑んで小さく手を上げてくれた。
ちょうど次の電車が来たので、電車に乗り込む。
電車に揺られながら今しがた起きたことを反芻していた。
ほんの5分程度の出来事だ。それでも不思議と克明に(こうして仔細に書き記せるくらいに)思い出せた。
そこに居合わせた人たちの顔や声を思い出していたら、自然と頬が緩んでくるのがわかった。「いいことをした」という満足感ではない(と思う)。なんというか、そこにいた名もなき人たちとの反射的な連携プレイの小気味良さに気分が良くなっていた。何より、その“反射的なこと”を同じ心持ちで動いてくれた人が数人もいたことが嬉しかったのだ。と思う。

人としてどう振る舞うべきか?何を言ったらいけないか?何を聞いたらいけないか?といった「人として」という問いが日に日に増えている。「多様性の時代」といえばその通りなのかもしれないけれど、ちょっとした意識のズレや軽率な発言で、人生から退場させんとするほどの強い「正義心」が社会一体に充満していることに、一抹の不安すら感じるようになった。
そんなことだから、僕自身も人とのやりとりにおいて、何か言いたいことがあっても一拍置いて言葉を選んで反応をしたり、礼節という名を借りた「1枚隔てた会話」をしたりすることが、もはや当たり前の「身だしなみ」のように身についている。「本音と建前」という言葉は前時代の言葉に感じるほどだ。
でも、そういう中にあって、この日の“反射的なこと”は、大袈裟なことを言えば、僕にとっては救いのようなものすら感じられた。
この日会った人とは金輪際会うことはないんだろう。
それでもどこかでまた会えるような気もしている。
いや、正確なことを言えば、「反射的に手を取り合える人たち」と、またどこかで会えると信じることができている、ということだろう。
終着駅に着いた時、二日酔いは彼方に消えていることに気がついた。
見上げれば、晩春特有の心地よい陽の光が舞っていた。
文・写真:Takapi